
後遺障害等級認定手続の基本
Procedure
交通事故による被害で後遺障害が残ると、その等級に応じた賠償金を請求することができます。等級の数字が小さいほど(症状が重いほど)高額な損害賠償請求が可能になりますが、実際の症状に合った等級が認められるかどうかは申請の仕方にもよります。適正な損害賠償を受け取るために、正しい手続を理解することが大切です。
- 1. 後遺障害等級とは
- 2. 後遺障害等級の2つの申請方法と認定までの流れ
- 2.1. 被害者請求
- 2.1.1. 被害者|手続に必要な書類を自賠責保険会社に提出し、自賠責保険金を請求
- 2.1.2. 自賠責保険会社|被害者が提出した書類の内容を確認し、損害保険料率算出機構に送付
- 2.1.3. 損害保険料率算出機構|被害者が提出した書類の内容を確認し、損害保険料率算出機構に送付
- 2.1.4. 自賠責保険会社|審査結果を踏まえて後遺障害等級を認定し、被害者に通知
- 2.1.5. 被害者が準備する必要のある書類
- 2.1.6. 被害者が準備する必要のある書類
- 2.2. 事前認定
- 2.2.1. 加害者側任意保険会社|手続に必要な書類を医療機関や被害者から収集し、自賠責保険会社に提出
- 2.2.2. 自賠責保険会社|提出された書類の内容を確認し、損害保険料率算出機構に送付
- 2.2.3. 損害保険料率算出機構|書類をもとに審査を行い、審査結果を自賠責保険会社に報告
- 2.2.4. 自賠責保険会社|審査結果を踏まえて後遺障害等級を認定し、加害者側任意保険会社を通じて被害者に通知
- 2.2.5. 被害者が準備する必要のある書類
- 3. 認定結果に納得できない場合
- 4. 後遺障害等級認定手続を弁護士に依頼するメリット
- 4.1. 適切な等級認定を受けることで、賠償金の増額につながりやすい
- 4.2. 申請手続の手間や精神的負担を軽減できる
- 4.3. 万が一「非該当」となった場合にも、異議申し立てなどの対応ができる
- 5. 後遺障害等級認定手続は弁護士にご相談を
後遺障害等級とは
後遺障害等級とは、国が交通事故などで体に残った後遺症の程度を1級から14級までの等級に分類したものです。例えば、遷延性意識障害のように意識がなく常時介護が必要な状態では1級、高次脳機能障害で身の回りのことはできるものの就労はできない、もしくは困難な状態は3級、といった具合に障害の内容や部位、程度などによって異なります。後遺障害の具体的な内容と該当する等級は国土交通省のホームページよりご確認いただけます。
後遺障害等級の2つの申請方法と認定までの流れ
後遺障害等級は交通事故の被害者が自賠責保険に対して申請し、その内容をもとに中立機関である損害保険料率算出機構が審査・認定します。
申請方法は被害者自身が申請を行う「被害者請求」と、加害者側の任意保険会社を通じて行う「事前認定」の2種類があり、それぞれの特徴と流れは以下の通りです。
被害者請求
被害者請求は被害者自身が手続を行うため、書類の準備に手間がかかるものの、十分な材料を揃えた状態で申請でき、結果的に認定される可能性が高まるというメリットがあります。また、示談成立前に自賠責保険から賠償金の一部を受け取れるのも魅力です。
ただし、より正確な認定結果を得るためには専門知識が求められるため、弁護士に協力を仰ぐのが一般的です。
申請の流れ
被害者|手続に必要な書類を自賠責保険会社に提出し、自賠責保険金を請求
自賠責保険会社|被害者が提出した書類の内容を確認し、損害保険料率算出機構に送付
損害保険料率算出機構|被害者が提出した書類の内容を確認し、損害保険料率算出機構に送付
自賠責保険会社|審査結果を踏まえて後遺障害等級を認定し、被害者に通知
被害者が準備する必要のある書類
・診断書 ・後遺障害診断書 ・診療報酬明細書 ・画像検査資料(CT・MRI等) ・交通事故証明書 ・自賠責保険金請求書
・事故発生状況報告書 ・印鑑証明書 ・休業損害証明書 ・その他必要に応じた資料(介護記録、日常生活報告書など)
被害者が準備する必要のある書類
・診断書
・後遺障害診断書
・診療報酬明細書
・画像検査資料(CT・MRI等)
・交通事故証明書
・自賠責保険金請求書
・事故発生状況報告書
・印鑑証明書
・休業損害証明書
・その他必要に応じた資料(介護記録、日常生活報告書など)
事前認定
事前認定では、被害者請求と異なり加害者の任意保険会社が書類を準備するので時間と手間がかかりません。一方で、手続の透明性が担保されないため正確な等級認定に必要な書類が提出されず、実際よりも軽度な等級で認定されてしまうケースもあります。また、賠償金は示談成立後に一括払いされるのが基本で、先払いを受けることができません。
申請の流れ
加害者側任意保険会社|手続に必要な書類を医療機関や被害者から収集し、自賠責保険会社に提出
自賠責保険会社|提出された書類の内容を確認し、損害保険料率算出機構に送付
損害保険料率算出機構|書類をもとに審査を行い、審査結果を自賠責保険会社に報告
自賠責保険会社|審査結果を踏まえて後遺障害等級を認定し、加害者側任意保険会社を通じて被害者に通知
被害者が準備する必要のある書類
・後遺障害診断書(その他の書類は基本的に加害者側保険会社が収集)
認定結果に納得できない場合
後遺障害等級認定の申請を行っても等級が認められなかったり、実際の等級よりも軽い等級で認定されてしまうこともあります。そうなると十分な賠償金を受け取れない可能性があるので、被害者は結果を受けて「異議申し立て」を行う権利が与えられています。しかし、異議申し立てによって結果を覆すのは容易ではないため、事前にしっかり反論の根拠を明確にするべきでしょう。
異議申し立てを認めてもらうためには、以下のような点がポイントとなります。
・希望の等級が認定されなかった理由を確認し、もし提出資料に不足や不備があった場合は修正する
・被害者の症状や状態を正確に示すなど、認定に有利になる資料を追加提出する
・医師と相談のうえ、必要に応じて意見書や追加の検査を依頼する
後遺障害等級認定手続を弁護士に依頼するメリット
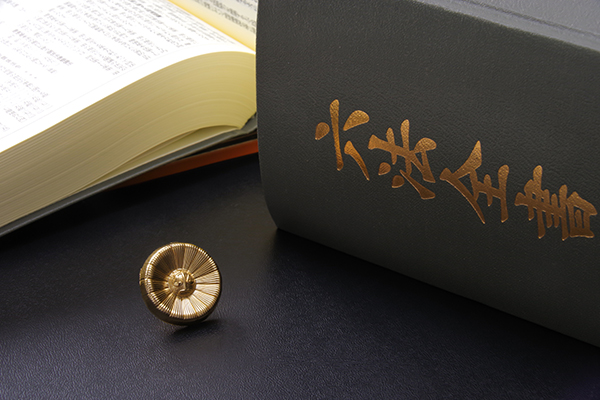
後遺障害等級認定手続は被害者自身で対応することもできますが、専門家である弁護士に一任するのがおすすめです。その理由は主に3つあります。
適切な等級認定を受けることで、賠償金の増額につながりやすい
後遺障害等級は、認定された等級によって損害賠償額が大きく変わります。弁護士に依頼すれば、事故の状況や被害者の症状をもとに、どの等級が適切かを的確に見極めたうえで必要な書類の準備や申請手続まで一貫してサポートしてもらえます。これは、法律・過去の判例・医学的知見に精通している弁護士だからこそ可能な対応であり、希望する等級の認定を受けるうえで大きな力となります。そのため、弁護士に手続を依頼することで最終的に十分な賠償金を受け取れる可能性が高まります。
申請手続の手間や精神的負担を軽減できる
申請方法の把握、提出書類の準備と作成、保険会社や医師とのやり取りなど、認定を受けるまでには多くの作業が発生するので、慣れていない方がすべて自身で対応するのは困難を極めます。特に医師が協力的でなかったり、保険会社から一方的な主張を突き付けられたりした場合、精神的にも疲弊してしまうでしょう。弁護士に依頼すれば手続をまとめて引き受けてくれるのでこうしたストレスから解放されます。
万が一「非該当」となった場合にも、異議申し立てなどの対応ができる
申請した等級が認定されなかった場合、そのまま諦めてしまう被害者の方も少なくありません。しかし、弁護士が付いていれば異議申し立てや追加資料の提出など再申請の手続を正確に進めることができ、一度決まった認定を覆すことができるケースもあります。
後遺障害等級認定手続は弁護士にご相談を
後遺障害等級認定手続は高度な専門知識が求められるものであり、被害者自身で対応するのは大変です。そのため、交通事故の被害によって後遺障害が残ることを医師から告げられたら早い段階で弁護士に相談しましょう。
当事務所では、後遺障害等級認定手続を入口からサポートします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。