
高次脳機能障害と診断されたら
Higher brain dysfunction
交通事故などで脳を損傷すると、典型的には、多彩な認知障害(注意・集中力障害、記憶・記銘力障害、遂行機能障害等)、行動障害や人格変化が症状として現れることがありますが、これを高次脳機能障害と言います。高次脳機能障害は身体が回復したとしても後遺症として残ることが多く、見た目ではわかりにくいものの生活や仕事に大きな支障を及ぼしてしまいます。
交通事故が原因で医師から高次脳機能障害と診断された場合は相手方に損害賠償を請求できますが、その症状や診断後の対応によって賠償金額が変わってくるので注意が必要です。
高次脳機能障害の代表的な症状
高次脳機能障害は外見上の外傷が見られず、本人に自覚がないケースも少なくありません。代表的な症状を以下に紹介するので、家族など第三者が事故前後で該当する変化がないかを観察することが大切です。
注意・集中力障害
・作業にミスが多い
・気が散りやすい
・作業が長続きしない 等
記憶・記銘力障害
・同じことを何度も質問する
・新しいことを覚えられない
・物の置き場所を忘れる 等
遂行機能障害
・計画を立てられない
・優先順位を決められない
・効率や段取りが悪い 等
社会的行動障害
・職場や社会のマナーやルールを守れない
・行動を抑制できない
・危険を予測・察知して回避できない 等
人格変化
・自発的に行動しない
・無気力
・怒りやすい
・自己中心的 等
神経症状
・うまく歩けない
・物をうまくつかめない
・言葉をうまく話せない 等
注意・集中力障害
・作業にミスが多い
・気が散りやすい
・作業が長続きしない 等
記憶・記銘力障害
・同じことを何度も質問する
・新しいことを覚えられない
・物の置き場所を忘れる 等
遂行機能障害
・計画を立てられない
・優先順位を決められない
・効率や段取りが悪い 等
社会的行動障害
・職場や社会のマナーやルールを守れない
・行動を抑制できない
・危険を予測・察知して回避できない 等
人格変化
・自発的に行動しない
・無気力
・怒りやすい
・自己中心的 等
神経症状
・うまく歩けない
・物をうまくつかめない
・言葉をうまく話せない 等
高次脳機能障害と診断されるケース
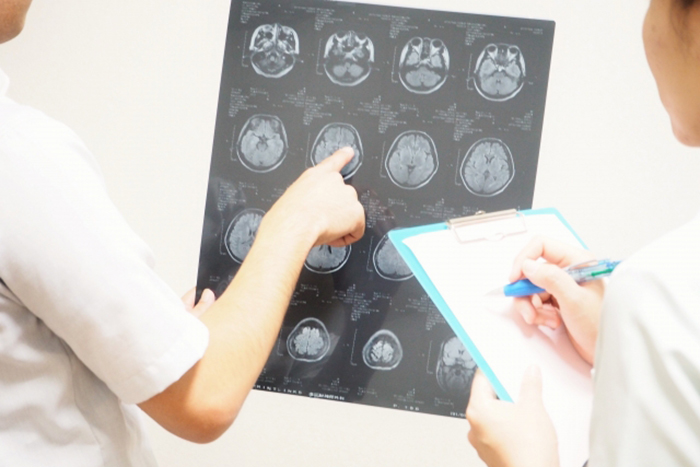
高次脳機能障害は、事故直後の意識障害があること、脳の画像診断で損傷・変化等が見られること、事故後に上記のような症状が起こっているケースで診断されることが多いです。同様のケースであれば、もし診断がなされていないとしても高次脳機能障害の発生を疑うことが必要です。
高次脳機能障害の後遺障害認定のポイント
高次脳機能障害は、症状によって後遺障害の等級が異なります。もし実際の症状よりも軽い等級で示談が成立してしまうと、本来受けられるはずの賠償金を受け取れなくなってしまうので、正確な症状の把握とそれを証明できる書類の収集が大切です。
後遺障害認定の前提
自賠責保険では、後遺障害診断書に高次脳機能障害の記載がされている場合や、そのような記載がなくとも主として以下のいずれかの場合に、高次脳機能障害の残存の有無が審査されることになります。
① 頭部外傷があり、経過の診断書で高次脳機能障害や脳の損傷等の診断がなされている場合
② 頭部外傷があり、経過の診断書で高次脳機能障害を示唆する症状(前述)がある場合
③ 経過の診断書に、初診時の頭部画像所見として頭蓋内の病変が記載されている場合
④ 初診時に頭部外傷の診断があり、事故後に一定のレベル以上の重い意識障害が少なくとも6時間以上、もしくは、健忘あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いた場合
⑤ その他、脳外傷による高次脳機能障害が疑われる場合
後遺障害等級
高次脳機能障害にまつわる状態と適用される可能性の高い等級(目安)は以下の通りです。
1級 … 食事・入浴・用便・更衣など生命維持に必要な動作に全面的介護が必要
2級 … 生命維持に必要な動作や外出等に、状況によって介護・監視・声掛けが必要
3級 … 日常生活で介護は不要だが、働くことが困難
5級 … 単純な繰り返し作業は可能だが新しい作業ができない等、作業能力の制限がある
7級 … 一般就労はできるが、作業中のミスや物忘れなどが頻繁に起こる
9級 … 問題解決能力や作業効率に問題がある
提出資料
高次脳機能障害の後遺障害認定のためには、脳の損傷状態、診断結果、被害者の症状等を確認する必要があるため、CT・MRIなどによる頭部の画像検査資料、そして診断書・後遺障害診断書が後遺障害等級認定に欠かせません。いずれも事故発生直後から症状固定までの経過がわかるような形での提出が求められます。
また、医師が作成する「神経系統の障害に関する医学的意見」や「頭部外傷後の意識障害についての所見」や、被害者の家族や介護者が作成する「日常生活状況報告」といった書類も提出が望まれます。
損害賠償の対象となる費用
高次脳機能障害となってしまうと長期にわたる生活支援が必要になるため、請求できる損害項目は後遺障害の重さによっては慰謝料や逸失利益だけでなく多岐にわたることになります。
後遺障害の内容によっては、将来にわたる介護費、車いす・電動ベッド等の将来の器具買換費用、自宅のバリアフリー改造費なども損害として認められることがあります。詳しくは「損害賠償額の基準と仕組み」より対象となる損害をご確認ください。
損害賠償額の基準と仕組み →高次脳機能障害と診断されたら弁護士にご相談を
高次脳機能障害は「見過ごされやすい障害」ですが、症状を正確に把握したうえでそれに見合った等級認定を受けることが、適正な損害賠償を受け取ることにつながります。
当事務所では、高次脳機能障害と診断された後の対応や後遺障害認定手続きをサポートします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。